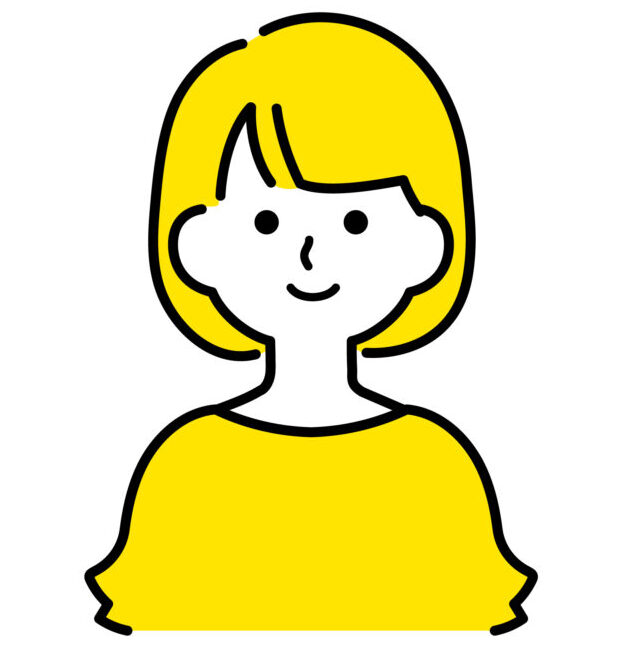
こんにちは、「プレミアム・エドゥトイ」を運営しているFP2級の紗希です。
「うちの子、小学1年生で二桁の掛け算を暗算で解けるようになったんです」
そんな話をすると、だいたいこう聞かれます。
- 「え、公文とかそろばんやってるの?」
- 「特別な習い事、何かしてるの?」
でも実は――計算に特化した習い事は一切ナシ!
しかも、“やらせる”ような勉強もゼロ。親がガミガミ言うことなく、気づけば自然と計算好きになっていたんです。
今回は、そんなわが子の実体験をベースに、家庭でも楽しく・無理なくできる「計算力アップの工夫」をご紹介します。
✅ この記事でわかること;
- 特別な習い事をしなくても、子どもの計算力を伸ばす方法
- 計算嫌いにならないために、親が意識したい声かけと関わり方
- 実際にわが家で使った市販教材・機器の活用法
- 小1で二桁の掛け算ができるようになった家庭での具体的ステップ
- 日常生活の中で数字と自然に触れる習慣づくりのヒント
実体験:二桁の掛け算を暗算でマスターするまでの道のり

わが家の子どもが、二桁の掛け算を暗算でスラスラ解けるようになるまでの流れを、リアルな体験をもとにご紹介します。
4歳ごろ:知育教室で「学ぶ楽しさ」と出会う
まず、うちの子は4歳頃まで知育教室(イクウェル・コペル)に通っていました。いわゆる「計算ドリル」ではなく、フラッシュカードやリズム遊びなど、遊び感覚で学ぶことが中心。
無理なく、楽しみながら数に親しむ土台ができたと感じています。
年中(5歳):足し算・引き算を自然に吸収
日常の中で「これとこれで何個?」「あと何個あるかな?」といった声かけを意識的に取り入れていくと、本人の中で自然と計算の感覚が芽生え始めました。
特に買い物ごっこやブロック遊びなど、数字と関わるシーンでの対話が効果的でした。
年長(6歳):割り算・一桁の掛け算が登場!
市販の簡単な教材を、子どものペースで少しずつ導入。「できた!」「わかった!」という成功体験を積み重ねることで、学びへのモチベーションがぐんぐんアップ。
この頃には一桁の掛け算や、簡単な割り算も理解できるようになっていました。
小学1年生:二桁の掛け算も暗算でスイスイ
一桁の掛け算がある程度スムーズにできるようになったタイミングで、二桁の掛け算のコツ(10のまとまりを意識するなど)を教えてみたところ、思いのほかすんなりと理解!
「なるほど、こうすれば暗算できるんだ」と、自分なりにやり方を工夫しながら楽しんで取り組む姿勢が育ってきたのを感じました。
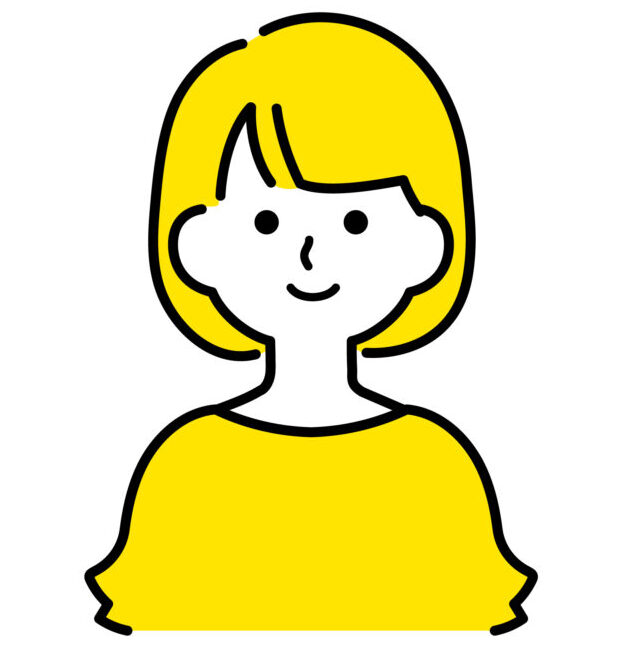
無理に詰め込むのではなく、子どもの興味が湧いたタイミングを逃さず、少しずつサポートすることが大切だと実感しています。
わが家の実践!家庭でできる「計算力アップ」の工夫

子どもが「計算って楽しい!」と思えるようになるために、わが家ではいろんな工夫を試してきました。特別なことはしていませんが、ちょっとした日常の関わりの中で、自然と計算力が育っていったと感じています。
市販の教材は“量より質”でじっくりと
市販のドリルには一緒に取り組みましたが、重視したのは「たくさんやる」ことではなく、「ちゃんとわかる」こと。
1問ごとに意味を考えながら、子どものペースでゆっくり進めていきました。
「この計算って、どんなときに使うんだろう?」と一緒に考えることで、数字がただの記号ではなく、生活と結びついた“意味のあるもの”として理解できるようになります。そんな学び方を意識しながら、わが家で実際に活用してきた教材をご紹介します。
電卓を自由に触らせて「数字=おもしろい」に
幼児期には、電卓を渡して「好きに触っていいよ」と自由に遊ばせていました。
最初は意味もわからずボタンを押していましたが、「数字を操作すると結果が出る」こと自体が刺激になったようです。
数字を“教え込む”のではなく、まずは触れて、遊んで、親しむことが大事だと感じました。
「なんだか楽しい」という感覚が、のちの学習意欲にもつながっていきます。
わが家で使っていたものとは少し違いますが、以下のような電卓があれば、もっと楽しく数字とふれあうことができるかもしれませんね。遊び心のあるデザインやボタンの押しやすさも、子どもにとっては大事なポイントです。
ピコトレで“遊びながら”自然と身につく

ゲーム感覚で計算練習ができる「ピコトレ」は、わが家でも大活躍。何よりよかったのは、親が声をかけなくても、自分から進んで取り組んでいたことです。
「今日は新記録!」といったゲーム内の目標がやる気を引き出してくれたようで、遊んでいるうちに自然と暗算が得意になっていきました。
さらに、夢中になって取り組んでくれるおかげで、親としても「学習させなきゃ」というプレッシャーや罪悪感がなく、安心して見守ることができたのも嬉しいポイントでした。
二桁の掛け算は「分解して考える」コツを伝える
少し慣れてきたタイミングで、計算を分けて考えるコツを教えてみました。たとえば、
「14×23」という問題が出てきたときには、
- まず「10×23=230」
- 次に「4×23=92」
- 最後に「230+92=322」
このように、「10と4に分けて、それぞれ掛ける」という方法を教えると、「なるほど!」とすんなり理解。
一気に二桁の掛け算のハードルが下がったようです。
日常会話で問題を出す→できたら全力で褒める!
日常生活の中でも、ちょっとしたスキマ時間に「これとこれで何個?」「あといくつあったら◯になるかな?」など、クイズのように声をかけていました。
そして、できたときは全力で褒める!
ちょっと大げさなくらいリアクションして、「できた!すごいね!」と伝えると、自己肯定感とやる気が一気にアップします。
(番外編)散歩中も「数字遊び」のチャンス!
外を歩いているときも、数字に触れるチャンスはたくさんあります。
- 「この看板の数字、読める?」
- 「車のナンバー、足し算してみようか」
- 「自販機で一番大きな数字はどれだと思う?」
こんなふうに、数字を“遊び”に変える工夫をすることで、無理なく興味を持ち続けてくれました。
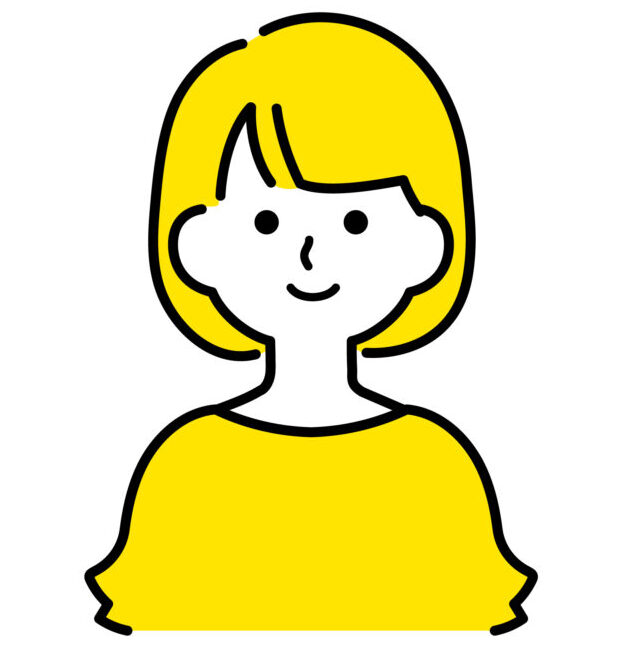
どれもすぐにできることばかりですが、こうした積み重ねが「数字が好き」「計算が得意かも」という気持ちにつながっていったように思います。
ぜひ、ご家庭でもできそうなところから取り入れてみてくださいね。
無理なく、「計算って楽しい」と思える環境づくりを
小さな子どもの計算力を伸ばすうえで、親が焦って「早くできるようにしなきゃ」とプレッシャーを感じる必要はありません。
むしろ、大切なのは子ども自身が“数字っておもしろい”と思える環境づくりです。
わが家では、以下のようなスタイルで家庭学習を続けてきました:
- 計算ドリルを毎日やる習慣はつけていない
- 計算のために塾にも通っていない
- 無理やりやらせたことも一度もない
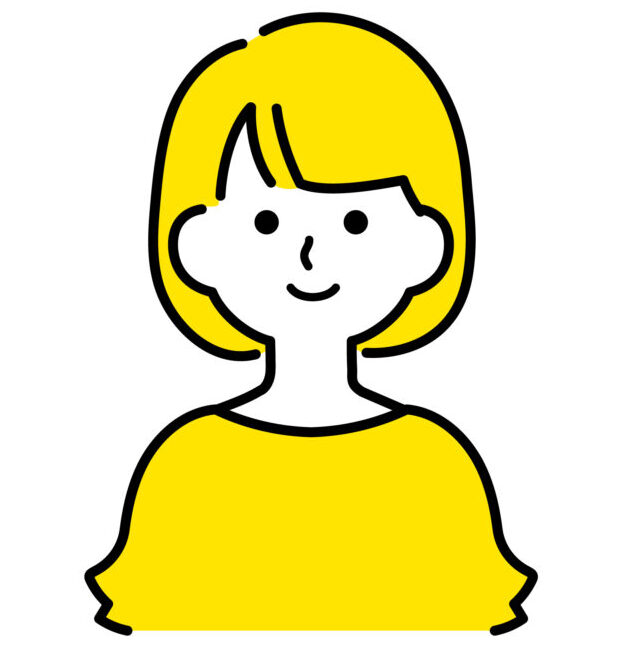
それでも、日々の生活の中で「ちょっとでも楽しい!」「できたら嬉しい!」という経験を重ねることで、自然と計算への興味が育ち、気づけば計算力がしっかり身についていたと感じています。
計算力を伸ばすには、必ずしも特別な教材やハードなトレーニングは必要ありません。
親子でゆるやかに関わりながら、無理なく、楽しく取り組める家庭学習の工夫があれば、それで十分です。
まとめ
子どもの計算力を伸ばすために大切なのは、ドリルや詰め込みではなく、「数字っておもしろい!」という気持ちを育てることです。
家庭でちょっと意識するだけで、計算に対する興味と理解はぐんと深まります。
計算が得意な子は、「早くからやらせた」「毎日ドリルをこなした」から育つわけではありません。
「楽しい」「わかる」「もっとやりたい」――そんな前向きな気持ちが、計算力の土台になります。
ちょっとした工夫で、子どもの可能性はどんどん広がります。
ぜひ今日から、ご家庭でもできることから始めてみてくださいね。
なお、『計算だけでなく、理系的な思考力そのものを伸ばしたい!』という方には、
楽しみながら論理的思考や空間認識を育てられるおもちゃを特集した、こちらの記事もおすすめです。ぜひあわせてチェックしてみてくださいね。

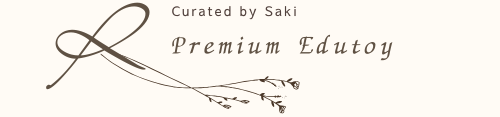
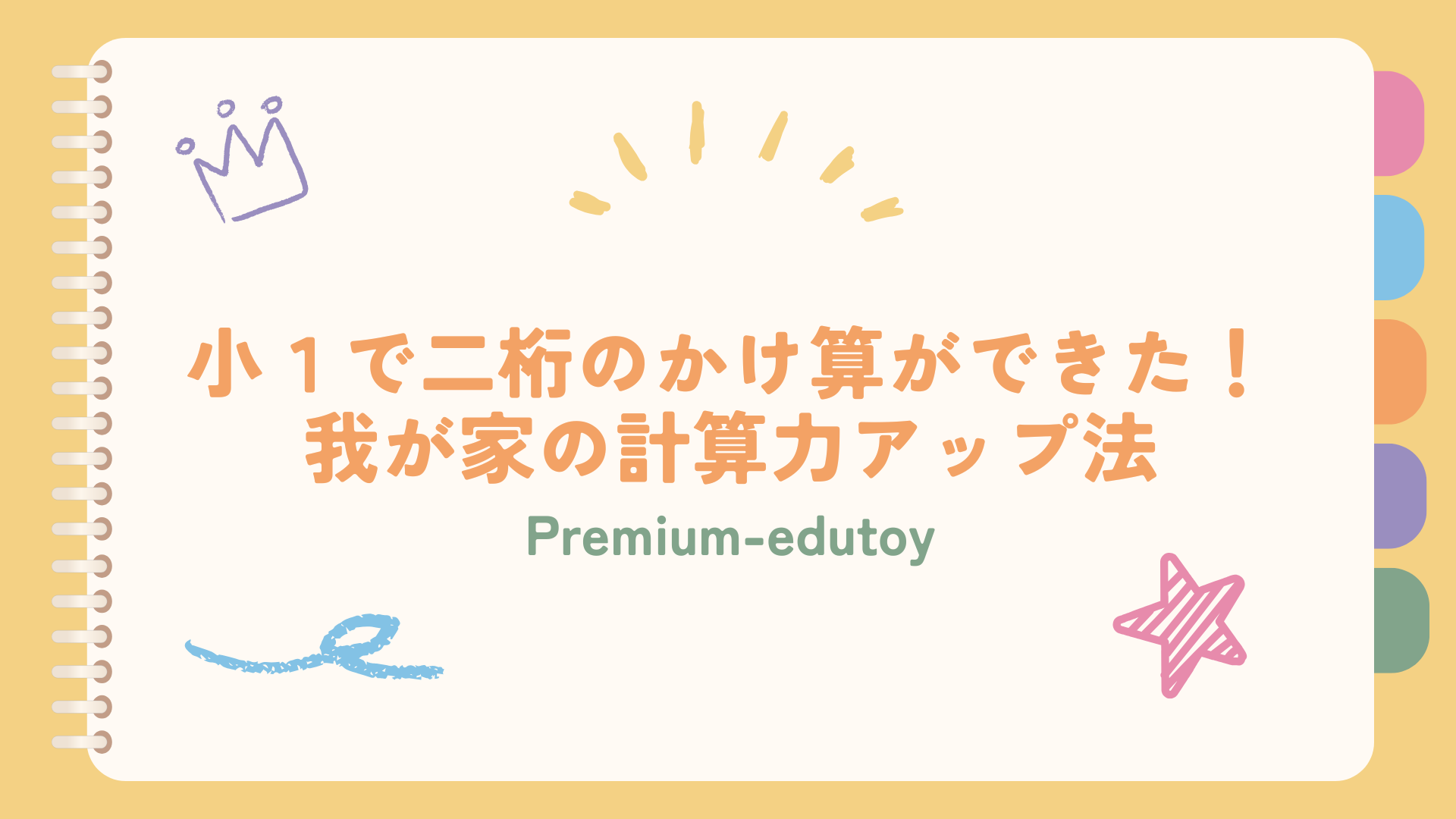
コメント