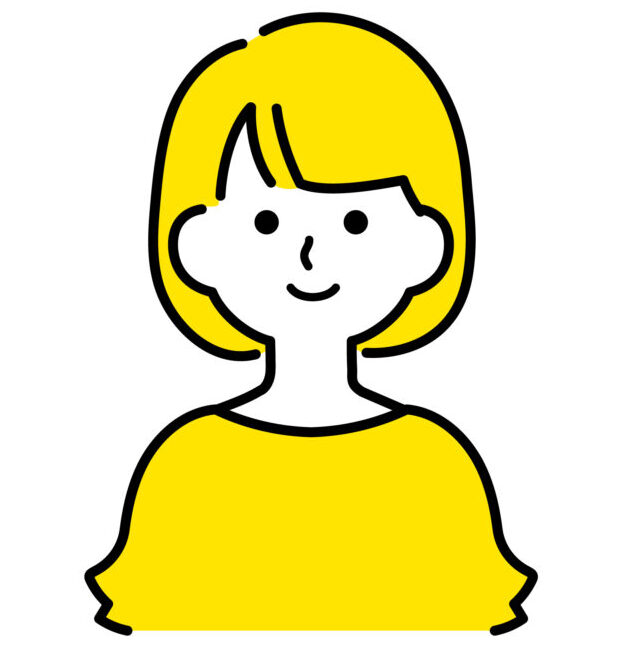
こんにちは、「プレミアム・エドゥトイ」を運営しているFP2級の紗希です。
「えっ、この漢字も読めるの!?」「どうしてそんな難しい言葉まで知ってるの…?」
――わが家では、そんな驚きの連続がありました。
6歳・年長の子どもが、小学校高学年レベルの漢字をスラスラと読みこなす姿に、親の私たちが一番びっくりしています。周りの大人からも「この漢字が読めるなんてすごいね!」と声をかけられるほどです。
でも実は、特別な勉強やハイレベルな教材には一切手を出していません。
“ある日突然できるようになった”というよりも、日々のちょっとした工夫の積み重ねが、大きな差につながったのだと思います。
この記事では、特別なことをせずに年長で漢字が読めるようになった、わが家の体験談と習慣をご紹介します。
✅ この記事でわかること;
- 年長で漢字がスラスラ読めるようになった子の、リアルな環境
- 難しいドリルなしでも読めるようになる理由
- 毎日の生活で無理なくできる、漢字に強くなる習慣
- 「動画見せすぎ」の罪悪感が減る!字幕の意外な効果
- 親の声かけ・関わり方で子どものやる気を引き出す方法
結論:特別なことはしていません。でも、“環境”は整えていました

「漢字ドリルを何度も繰り返す」
「小学校の教材を先取りして勉強する」
――そんな本格的な勉強は、わが家では一切していません。
それでも、年長の子どもが小学校高学年レベルの漢字までスラスラ読めるようになったのは、日々の生活の中に“読み”のチャンスを自然に取り入れていたからだと思います。
子どもにとって無理のない範囲で、楽しみながら文字と触れ合える環境を整えていたことが、大きな成果につながったのです。
具体的には、次に紹介するような習慣を家庭に取り入れていました。どれも特別なスキルや高価な教材は必要ありません。
どのご家庭でも、今日からすぐに実践できることばかりです。
我が家で実践していた4つの習慣

ここからは、年長で漢字がスラスラ読めるようになったわが子のために、家庭で取り入れていた具体的な習慣をご紹介します。
どれも特別な教材や指導は不要。親子で楽しみながら、自然と“漢字に触れる環境”をつくることを意識していました。
① 漢字つきの本を一緒にたくさん読む
市販の絵本や児童書には「ふりがな付き」が多いですが、我が家ではあえて漢字がたっぷり使われている本を選び、子どもと一緒に読むようにしていました。
難しい漢字が出てきたら、親が読んであげたり、「これ、なんて読むと思う?」と会話を交えたり。
すると、自然と子どもが漢字を“音と意味のセット”で覚えるようになったのです。
📌 ポイント:親子で「読む時間」を共有することが大切!
読み聞かせの時間に少しずつ漢字を意識するだけで、読解力や語彙力もアップします。
② フリガナ付きの“年齢相応の本”をどんどん渡す
「先取り」よりも、「等身大の興味」と「楽しい読書体験」を重視していました。
無理に難しい本を読ませるのではなく、年齢に合った面白いストーリーをたくさん用意。
たとえば、アニメのノベライズやキャラクターもの、図鑑など。
ふりがな付きなので無理なく読めて、「楽しいからもっと読みたい → 自然と漢字に触れる機会が増える」という好循環が生まれました。
📌 ポイント:「好きな内容」を選ぶことで、学びが自発的になる!
③ 字幕付きの映画・アニメ・動画を見せる(これが意外と効果大!)
正直に言うと、これが一番効果を感じた習慣かもしれません。
ディズニー映画や子ども向けアニメを「字幕オン」にして見せるだけ。
お気に入りの作品を繰り返し見ることで、目に入った漢字とセリフの音声がリンクして、自然に“読む力”が育つのを感じました。
✔ 親にとってもうれしいポイント:
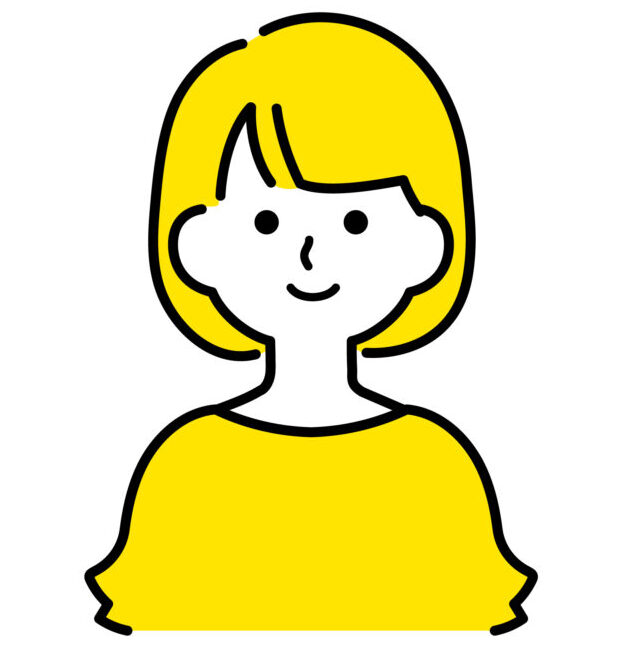
「動画ばかり見せていて大丈夫かな…」という罪悪感が減ります!
字幕がついていれば、立派な“読む練習”に変わるのです。
④ 少しでも読めたら全力で褒める!
「すごいね!」「よく読めたね!」「天才かも!」――
とにかく、読めたときはオーバーなくらいに褒めていました。
子どもは認められると、もっと挑戦したくなるもの。
無理に教え込むよりも、「楽しい・できた・またやりたい」という気持ちを育てた方が、結果的に力が伸びました。
📌 ポイント:自信と達成感が“学ぶ力”の原動力になる!
毎日の工夫が、“漢字力”を育てる大きな力に
今回ご紹介した4つの習慣は、どれも特別な教材や難しい準備は必要ありません。
日常の中にほんの少しの工夫と意識を加えるだけで、子どもは驚くほど漢字を吸収していきます。
大切なのは、「先取り」や「詰め込み」ではなく、子どもが楽しみながら“読むこと”に触れられる環境づくり。
最初はふりがなに頼っていても、「読めた!」「わかった!」という小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな自信につながっていきます。
実際、わが家では特別なトレーニングをしなくても、気がつけば年長で小学校高学年レベルの漢字を読めるようになっていたのです。
「うちの子も、もっと漢字が読めるようになってほしい」
そう感じているご家庭には、ぜひ今日から試してほしい方法ばかりです。
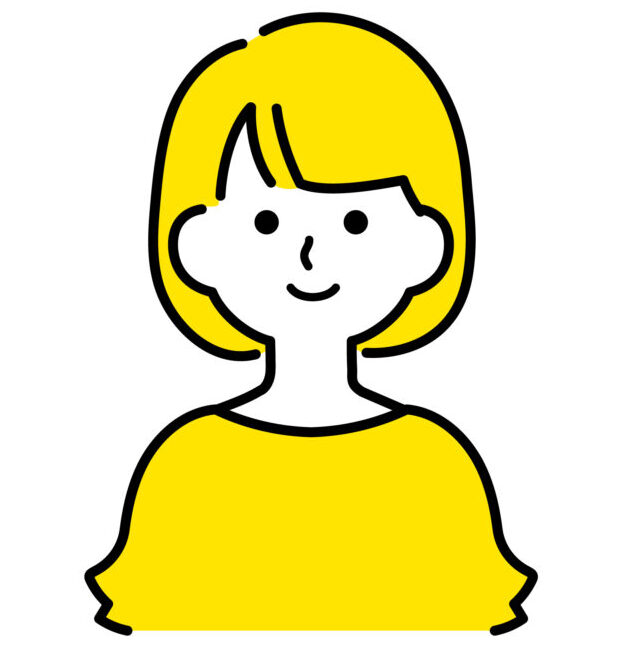
楽しみながら“読む力”を育てることが、漢字好きの第一歩になります。
よく聞かれる「漢字の書き取り」はどうしてる?

「漢字が読めるようになったのはすごいけど、書く方はどうしてるの?」
と、よく周りのママ友や親せきに聞かれます。
正直なところ、書く力については“焦らず、ゆっくり”がわが家のスタンスです。実際に取り組んでいるのは、年齢に合った市販のワークブックを、気が向いたときに少しずつやる程度。毎日びっちり漢字練習をしているわけではありません。
とはいえ、最近は「読める漢字が増えると、書くスピードも徐々に上がってくる」と感じています。
- 読みながら目で覚えていた漢字が、「これ、見たことある!」と書くときにも役立つ
- 字の形に自然と親しんでいるから、書き写しやすくなる
つまり、「読む力」がしっかり育っていれば、「書く力」もあとから自然とついてくるということ。
だから今は、無理に書かせるのではなく、まずは“読む楽しさ”を大切に。
「読めるようになってきたね!」「じゃあ今度はちょっと書いてみようか」と、自然に書く方にもつながっていけば十分だと考えています。
※参考に我が家で使用した教材を載せておきます👇
まとめ:ポイントは「環境づくり」と「楽しさ」
年長で漢字をスラスラ読めるようになったわが子の成長を通して、私たちが実感したのはこの3つです:
- 特別な教材や先取り学習は必要なし
- 「読む」「見る」環境を日常に取り入れることが大切
- 子どものやる気を“とことん褒めて”伸ばす
この3つを意識するだけで、自然と「読める漢字」がどんどん増えていきました。
親の気持ちもラクになる“学び方”を選ぼう
「ちゃんと勉強させなきゃ」と思うと、親も子もつい力が入ってしまいますよね。
でも、「楽しく取り組んでいたら、いつの間にか読めるようになっていた」――そんなスタイルが、子どもにとっても親にとっても一番ストレスが少なくて続けやすいのです。
ふりがな付きの本や字幕付きの動画なども、使い方次第で立派な学びのツールになります。
「動画ばかり見せてしまって…」という罪悪感も、今日からは少し手放してOK。
ぜひ、気軽に取り入れてみてくださいね!
このブログでは、子どもの成長をサポートする家庭環境づくりの一環として、
> 目的別のおもちゃ紹介
> おもちゃのサブスクサービス
などもご紹介しています。
おうち時間をもっと楽しく、もっと学びあるものにしたい方は、ぜひそちらも参考にしてみてくださいね!
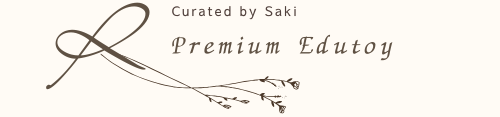
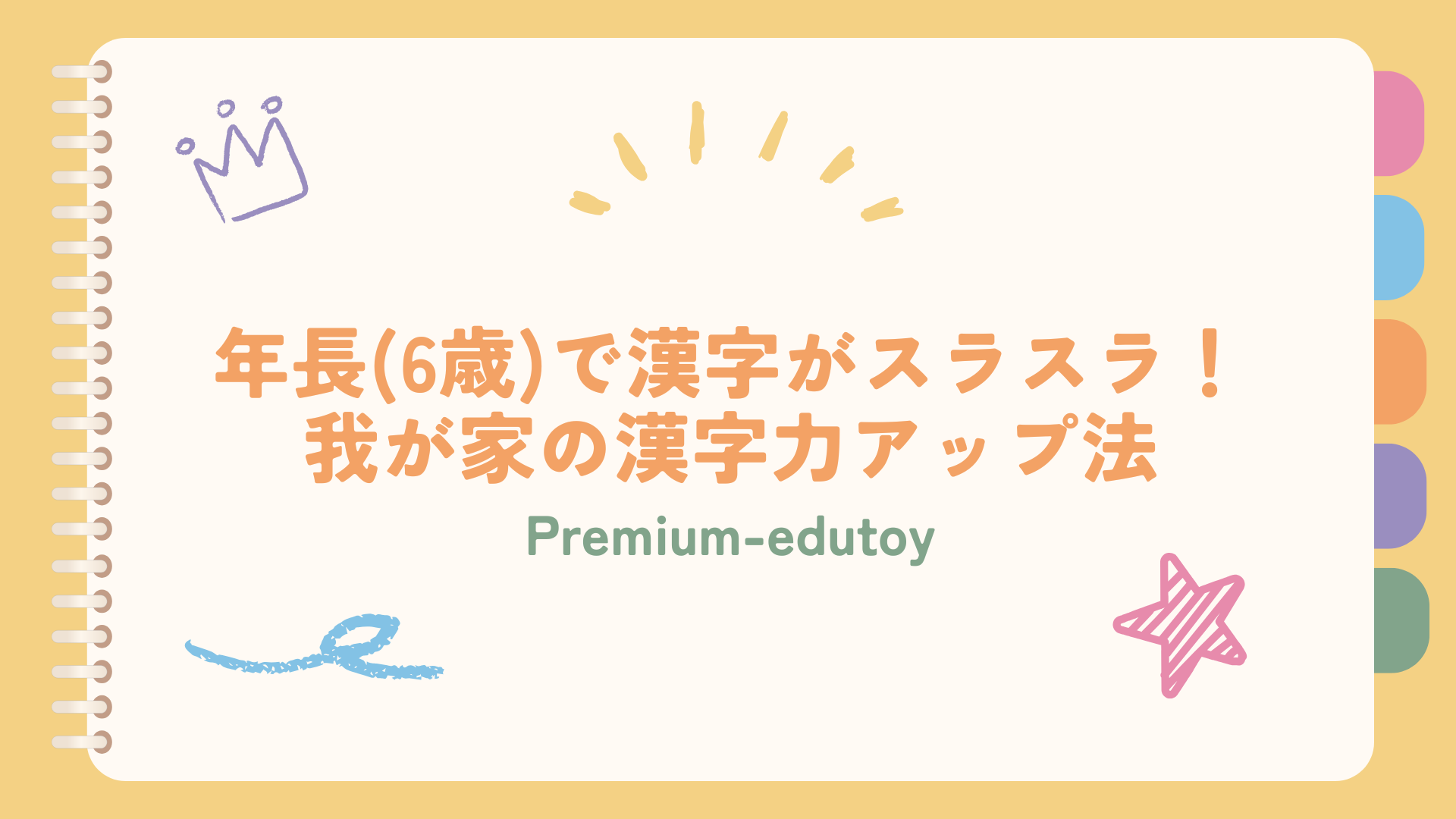
コメント